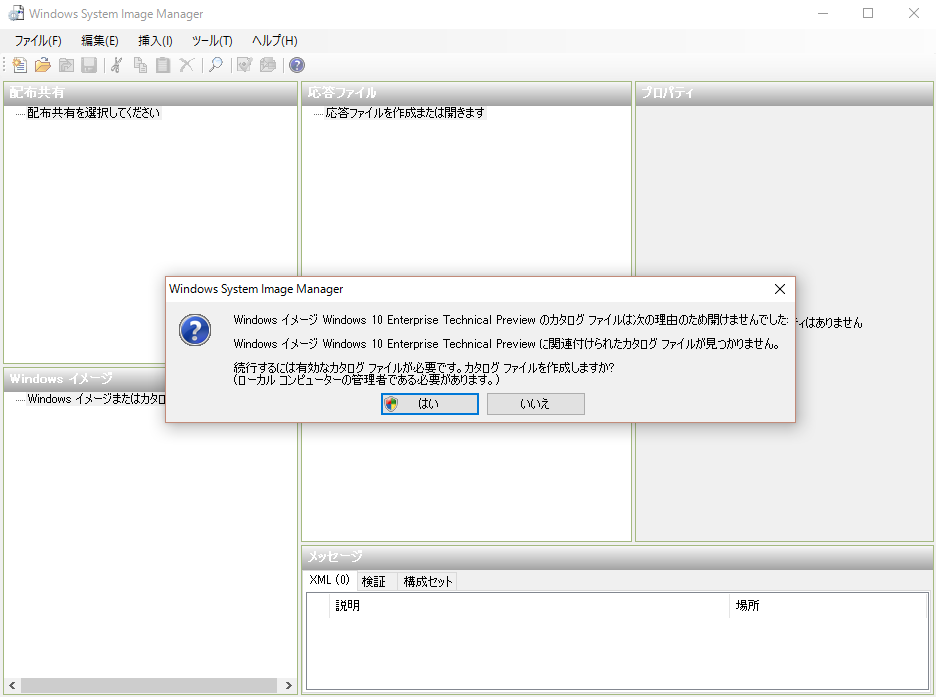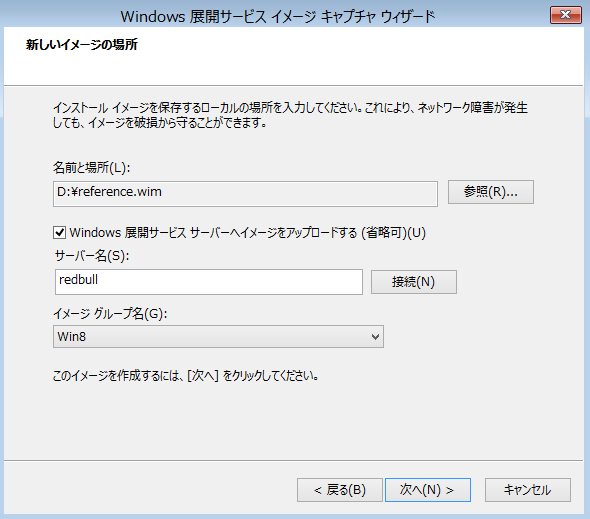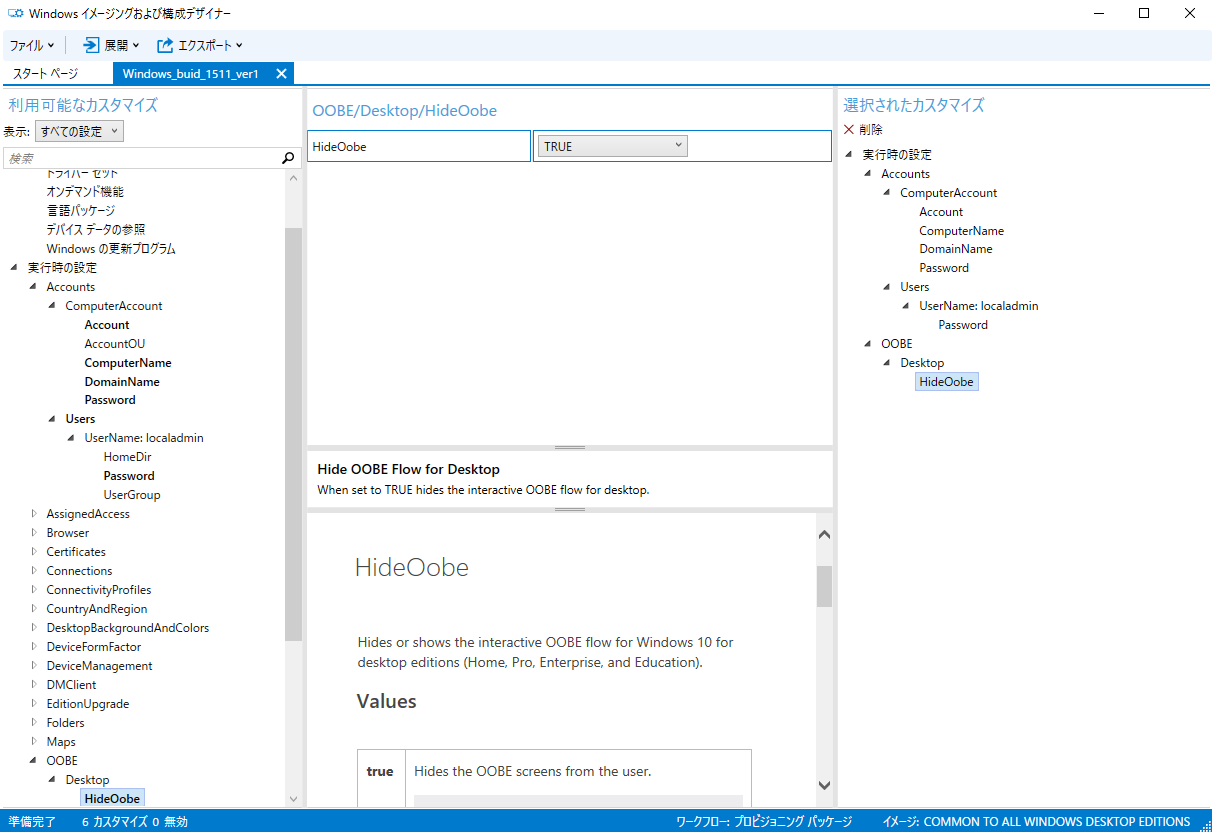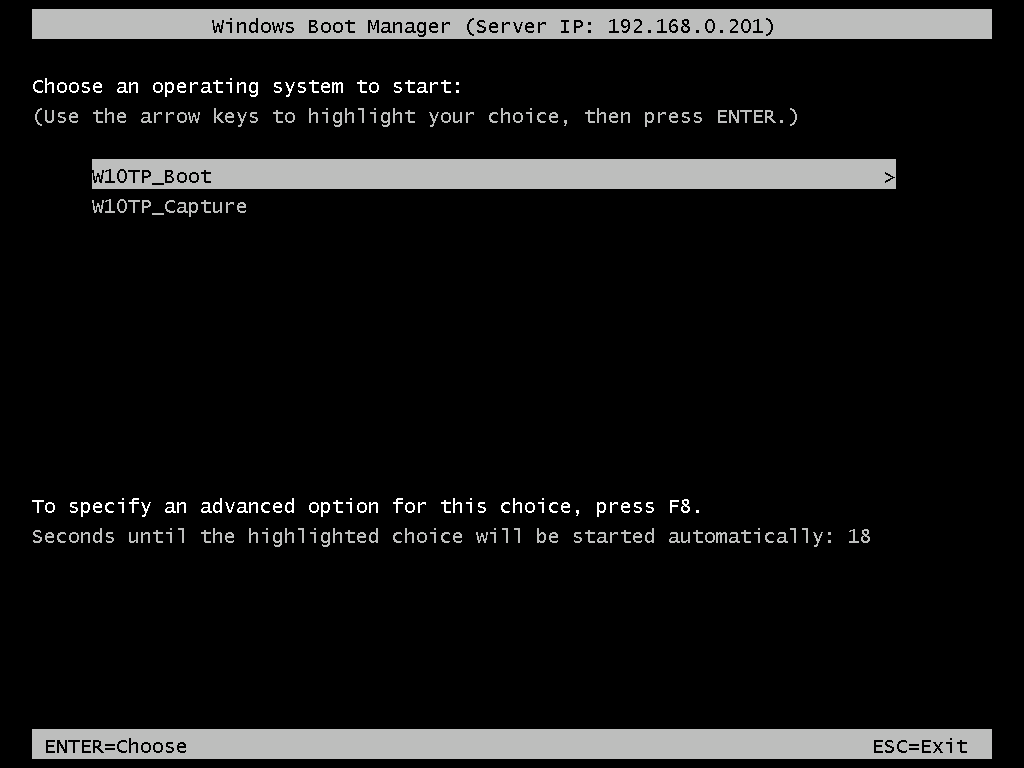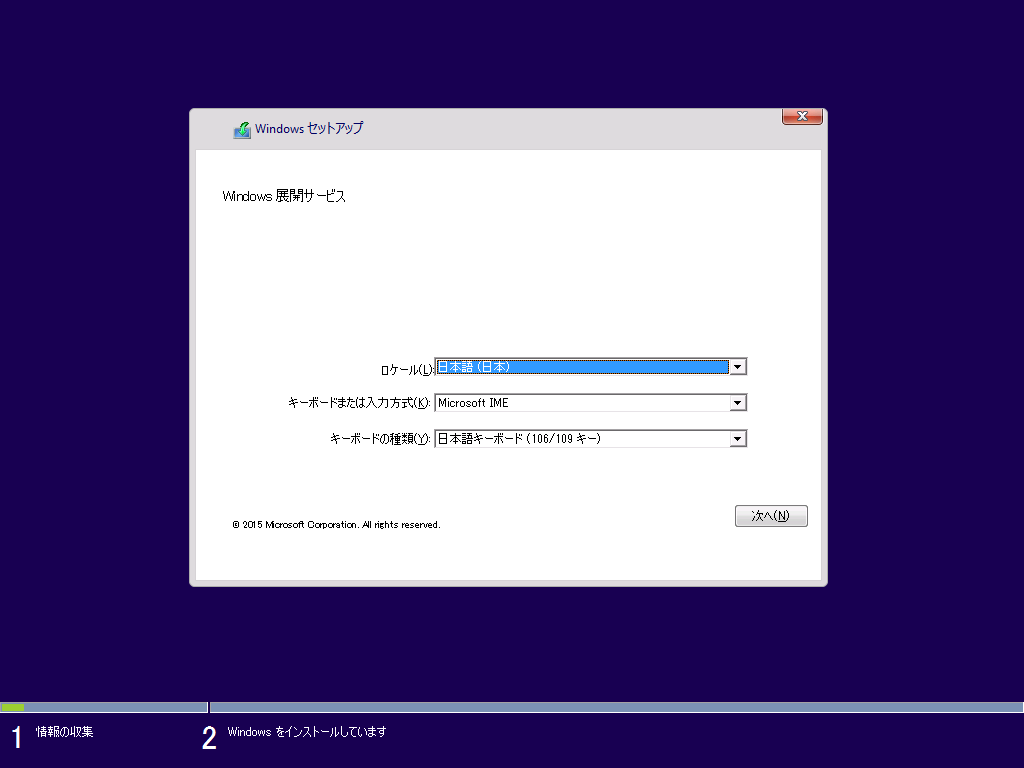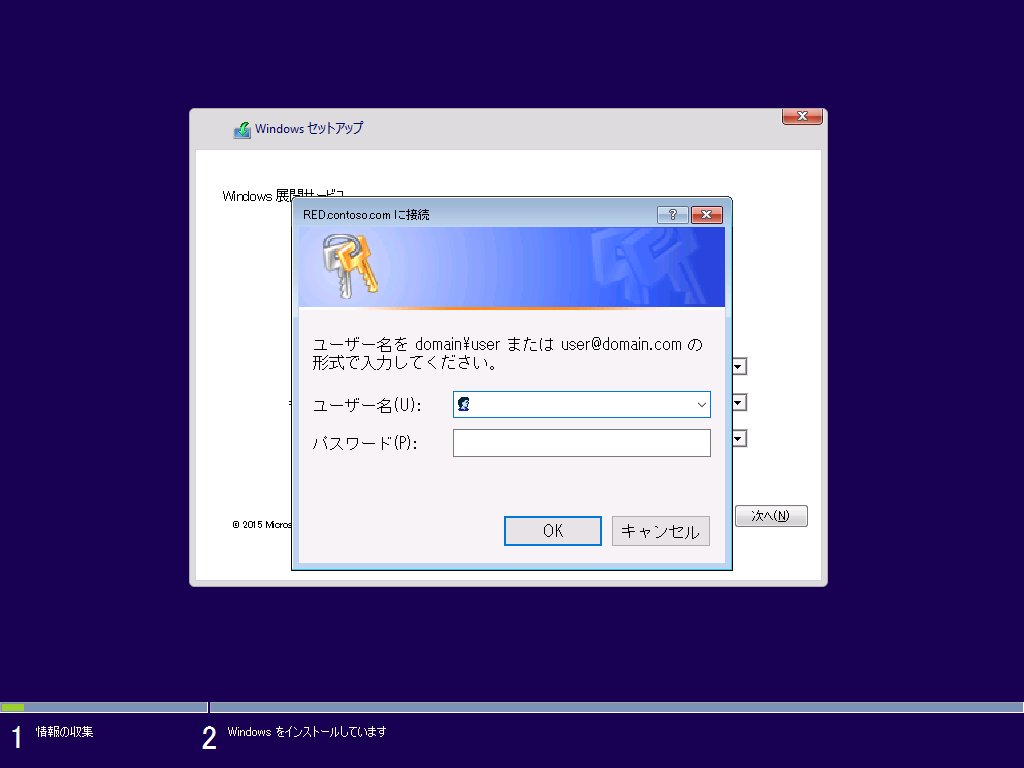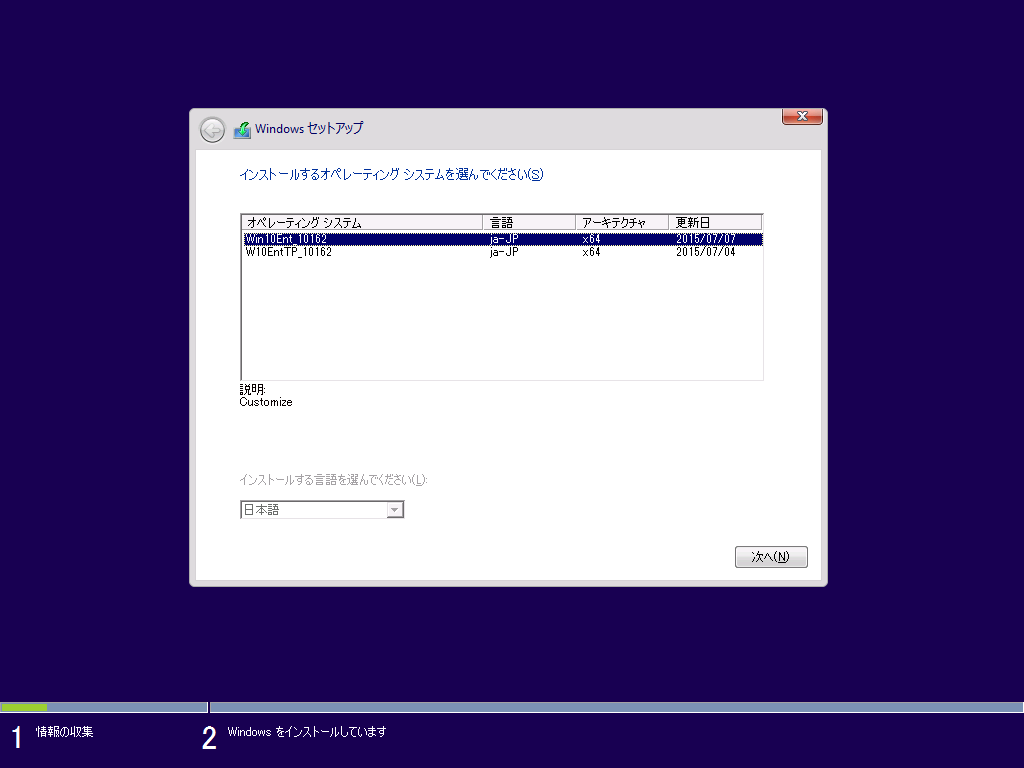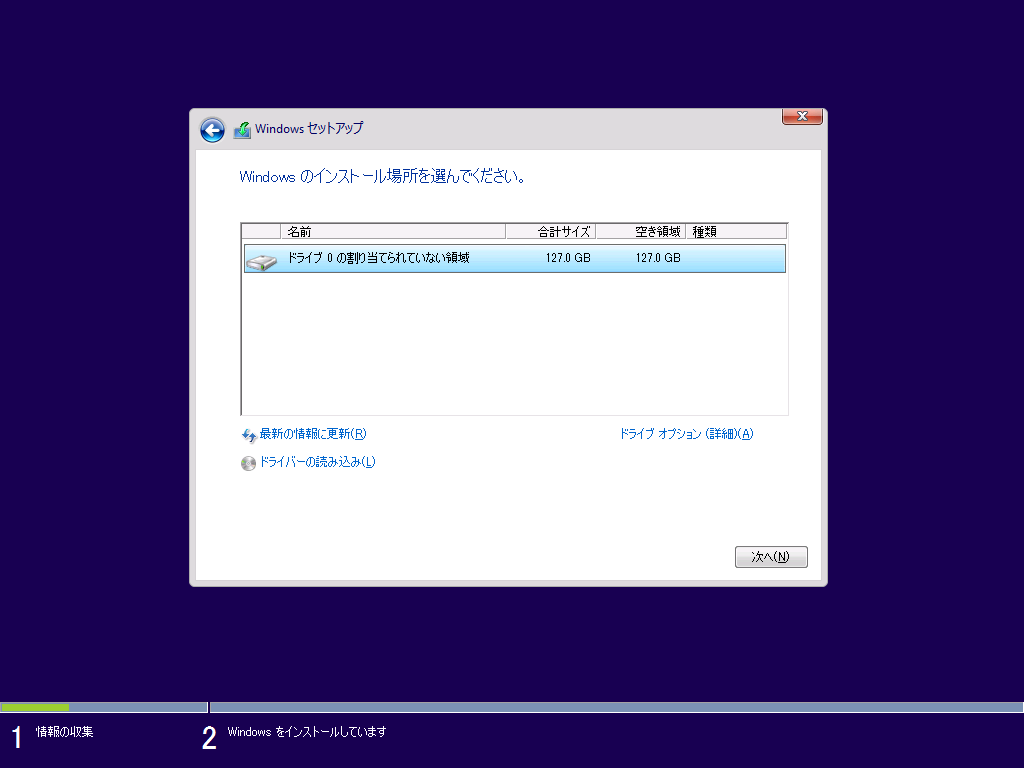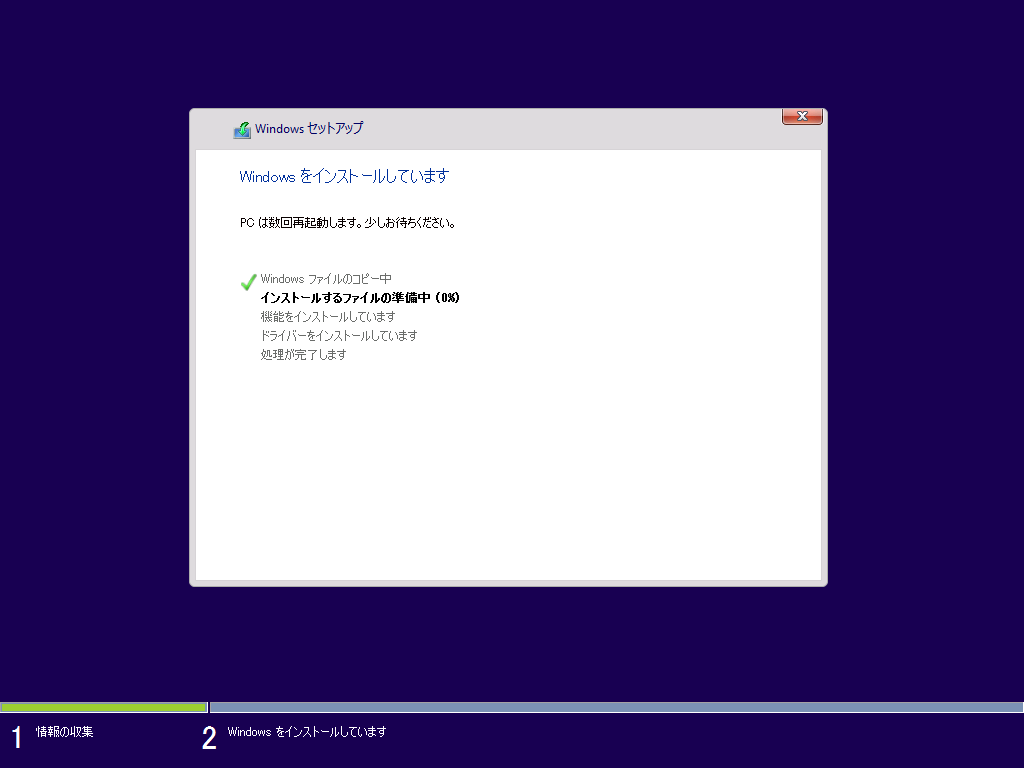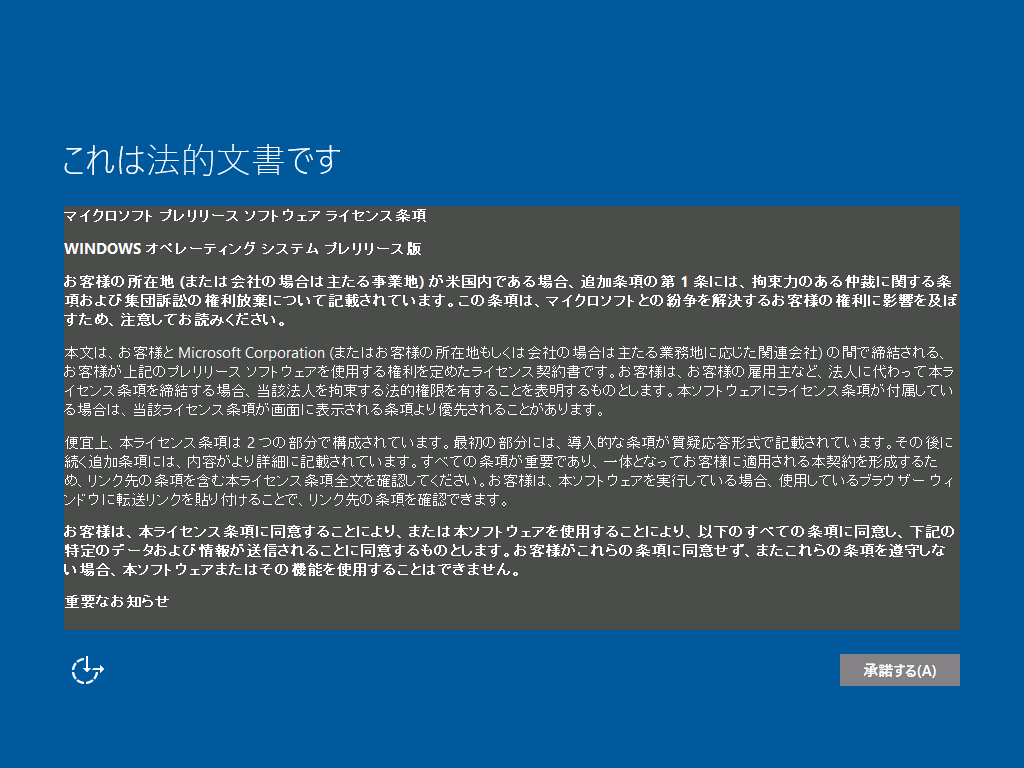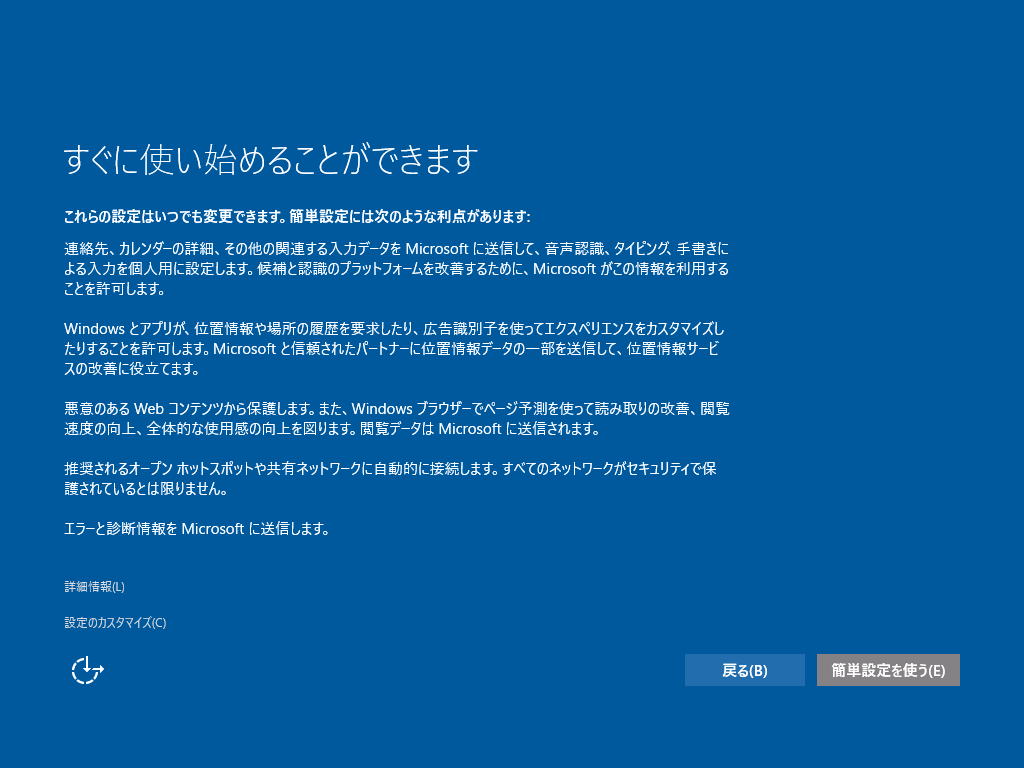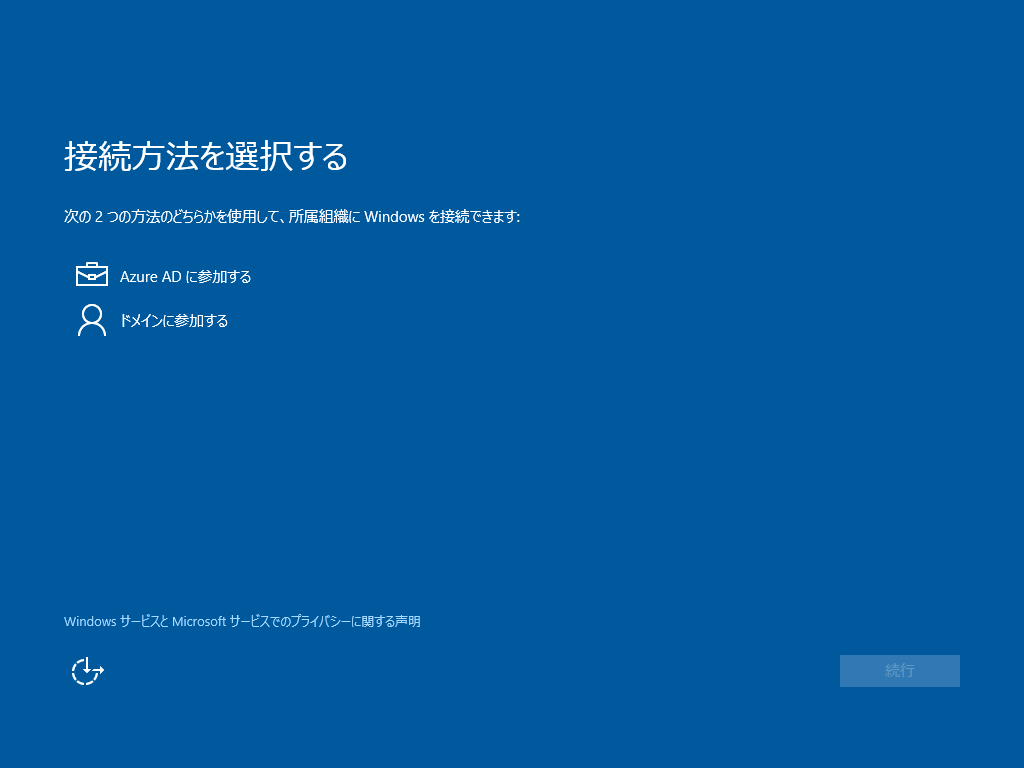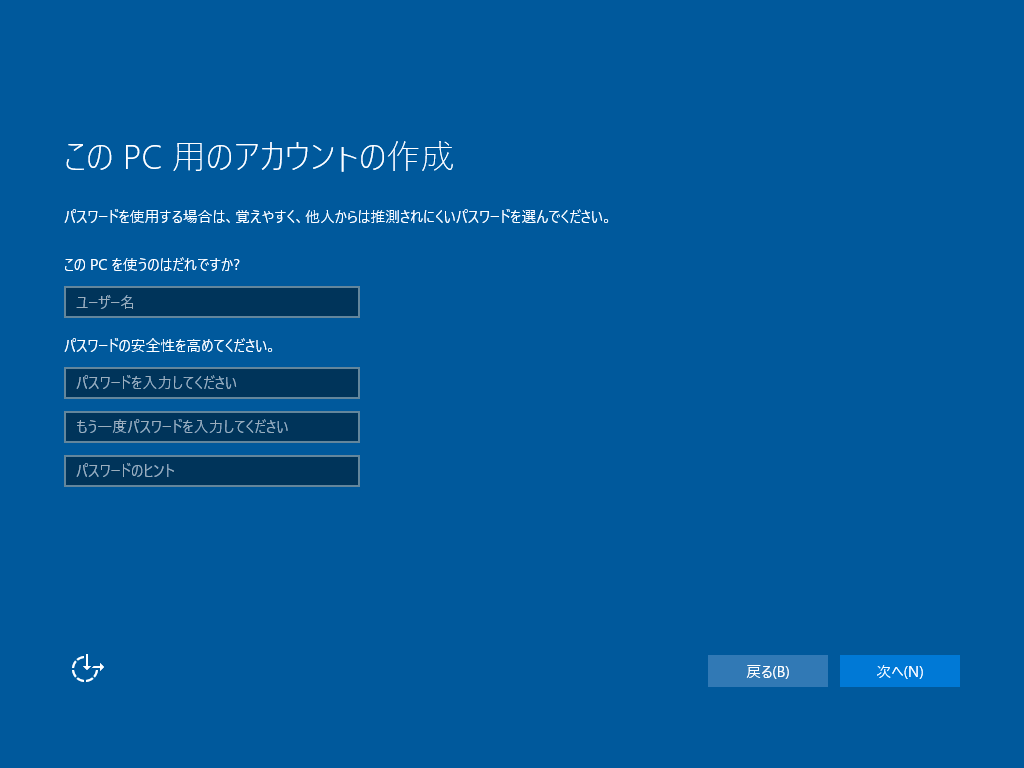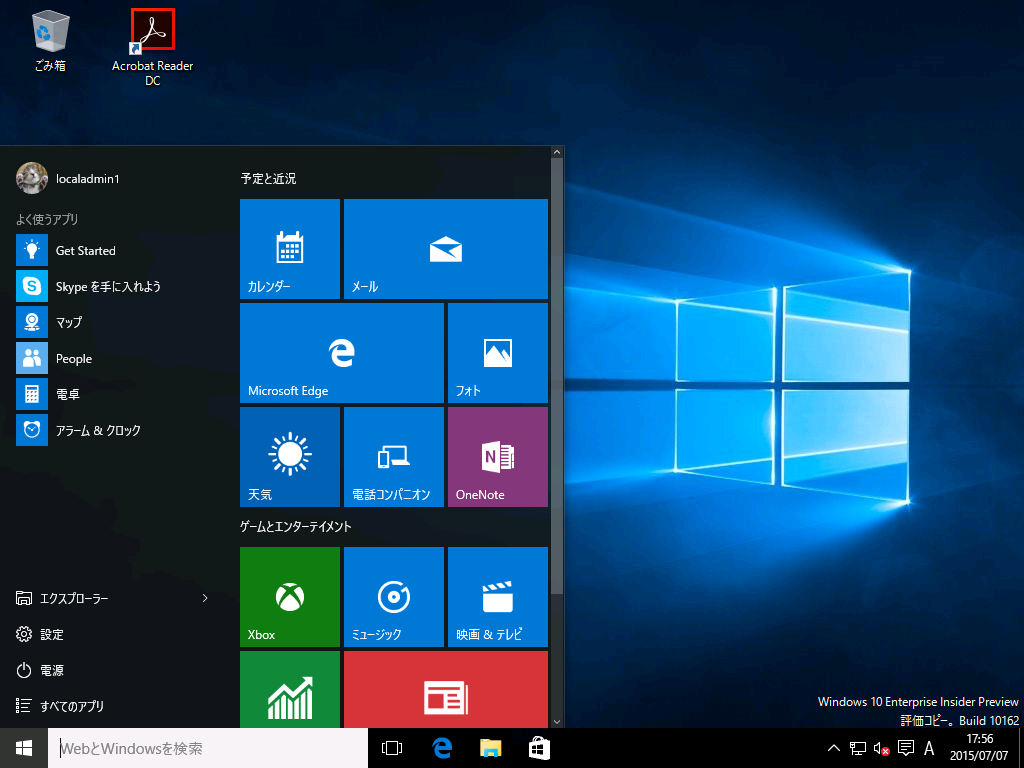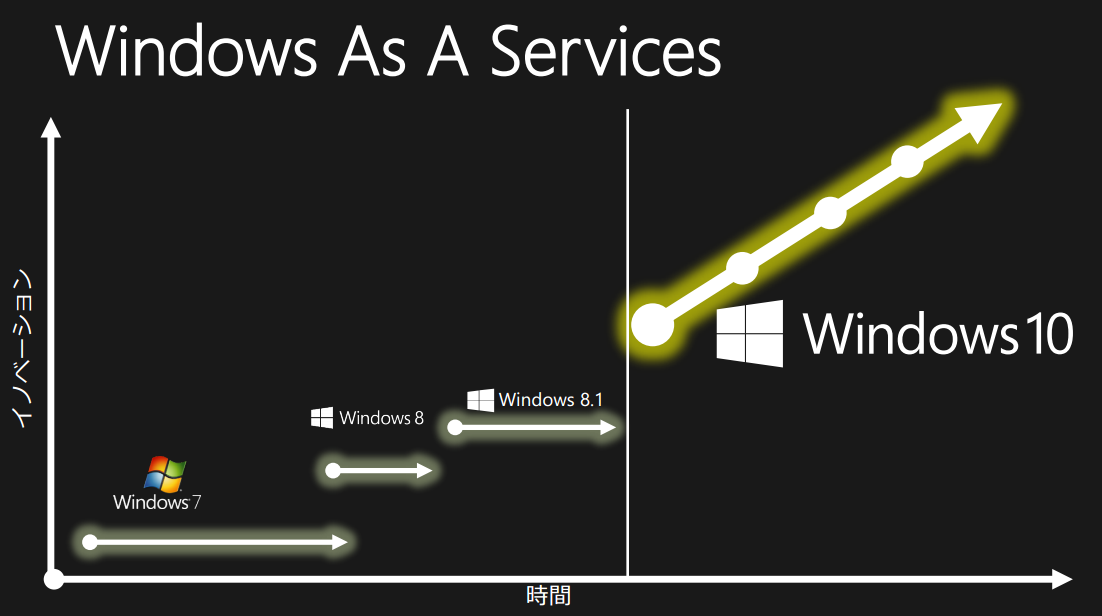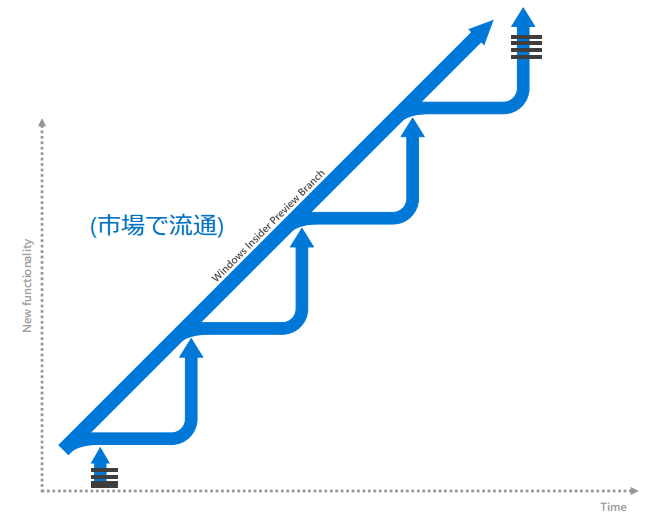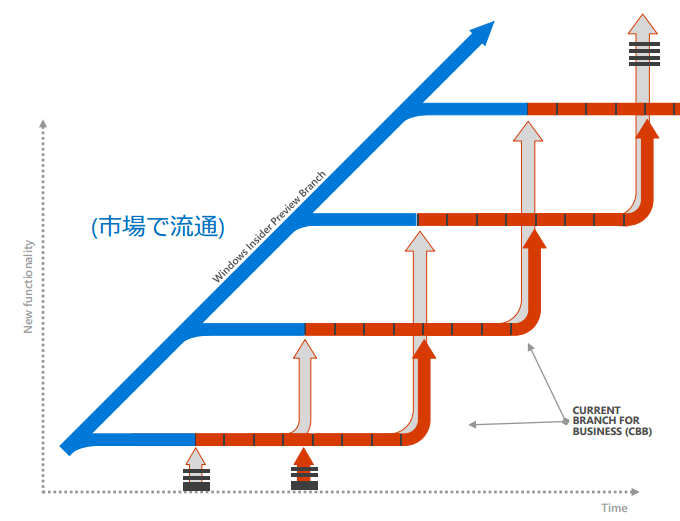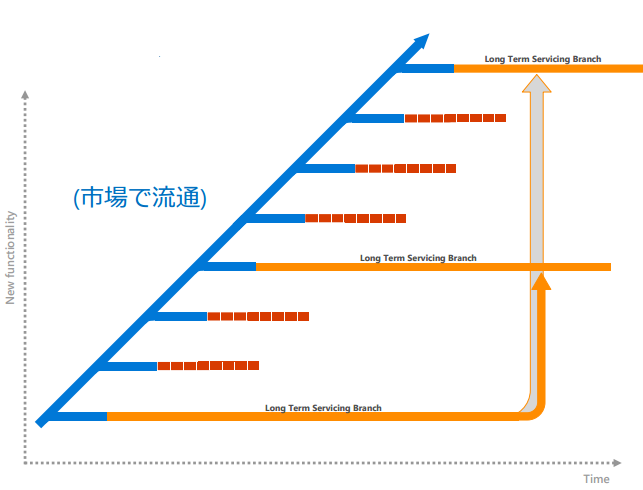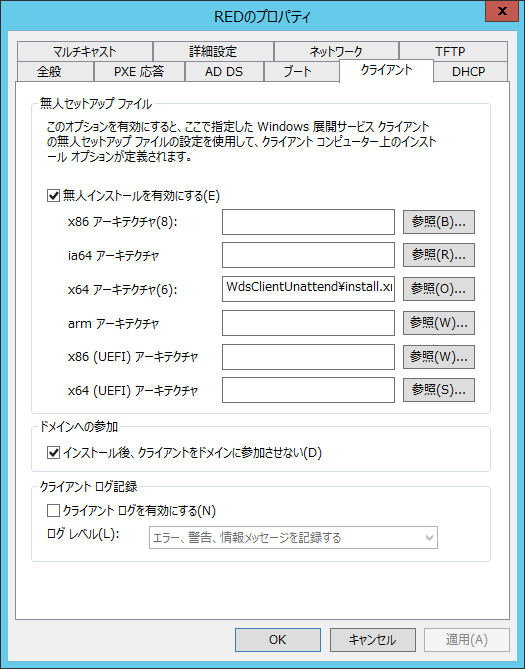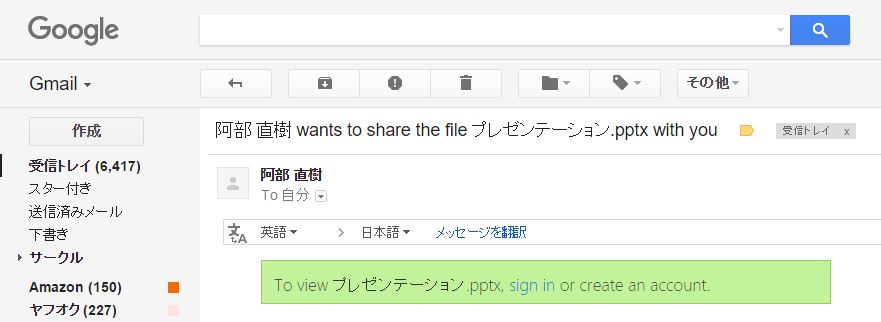前職は Microsoft のトレーナーとして活動していましたが、昨年ジョブチェンジして購読する書籍も変化してきました。そこで、どのような書籍を読んでいるが紹介いたします。
内容紹介:
ソフトウエア開発者専用に、「より良い人生」を送るためのノウハウ・スキルを網羅した、生き方バイブル本です。
プログラマーが良い人生を送るためには、技術習得法やキャリア構築法といったノウハウに加え、対人的な交渉・指導・意思疎通などをうまく行える能力や知恵、すなわちソフトスキルが不可欠です!
本書では、キャリアの築き方、自分の売り込み方、技術習得法、生産性の高め方といった仕事で成功する方法だけでなく、財産の築き方、心身の鍛え方、恋愛で成功する方法など、「人生全般をより良く生きる方法」を具体的に説明します。
私は、開発者ではありませんが、より良い人生を送るためのノウハウなどが書かれているようで海外ではかなり良書して紹介されており、日本語訳されたので購入してみました。まだ、届いていませんが楽しみな一冊です。
脱オンプレミス!クラウド時代の認証基盤Azure Active Directory完全解説
内容紹介:
アイデンティティ管理の新たな選択肢、IDaaS(Identity as a Service)を実現する、クラウド版Active Directoryを徹底解説!
“Modern Authentication with Azure Active Directory for Web Applications”(Microsoft Press, 2016)の、待望の日本語版が実現しました! Webアプリケーション向けに、Azure Active DirectoryによるID管理の仕組みと、その方法を解説します。原著者は米国マイクロソフト本社でAzure Active Directoryのプロダクトマネージャーを務めるVittorio Bertocci氏。日本語版の監訳は、日本マイクロソフトのインフラ系エバンジェリストである安納順一氏と、Microsoft MVPで、アイデンティティ分野で数多くの解説記事を執筆する富士榮尚寛氏が担当。米国と日本のスペシャリストたちがガッチリとタッグを組んだ1冊です。クラウド時代の企業システムを担う開発者、システムアーキテクト、インフラエンジニアにぜひお勧めします。
これはMSテクノロジを触っている人は納税義務がある一冊でしょうw
ITロードマップ 2016年版―情報通信技術は5年後こう変わる!
内容紹介:
本書は、ITをビジネスに活用する企業の経営者や企画部門の方、実際にITの開発や運用に携わる方々に対して、2016年以降のIT利活用のナビゲーションとなるべく、以下のような構成としている。・・・
こちらは、これからIT業界がどのように変化するかを推測するにあたり参考になる一冊です。
事例から学ぶ情報セキュリティ――基礎と対策と脅威のしくみ Software Design plus
内容紹介:
コンピュータシステムが社会インフラとして定着する中で,情報セキュリティに関する脅威はさまざまな分野や人に大きな影響をおよぼします。また,IT技術の進化に伴って複雑化し,さらに国境も超えるボーダーレスなものとなっています。そこで本書では,「情報漏洩」「サイバー攻撃」「脆弱性」「マルウェア」「フィッシング」「インターネットバンキング」の事例や脅威のしくみを説明し,それぞれの対策方法をまとめます。情報セキュリティの事例アーカイブとしても有用です。
セキュリティコンサルとして読んでおきたいかなと
サイバーセキュリティ2020 脅威の近未来予測 (NextPublishing)
内容紹介:
東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向かい、ICT、IoTがますます発展することは間違いありませんが、同時にサイバーセキュリティへの取り組みも転換期を迎えています。本書は2020年にどんなICT社会が実現し、それに伴いどんな脅威が予測されるのかを3部構成で解説しました。まず、テクノロジーが進展した2020年の生活を架空の物語として紹介、続いて専門家の寄稿により、次世代の技術とそのリスク、社会課題について詳しく解説します。最後に、3人の識者が今後のプライバシー問題を予想しています。これから5年、どのようなセキュリティの施策を考えるべきなのか、ユーザーと技術者、事業者が一緒に考えるために、必要な情報を提供します。
これもセキュリティコンサルとして読んでおきたいかな
[改訂新版]Windowsコマンドプロンプトポケットリファレンス
内容紹介:
「しばらくパスワードを変更していないユーザーを一覧にしたい」「ドメインが正常に動いているか確かめたい」「バッチの実行状況をイベントログに書き込みたい」「削除情報も含めてファイルを複製したい」-GUIの管理ツールではできないこんな操作もコマンドならたった1行で全部できる。Windows使いにとってコマンドは魔法の呪文ようなもの。本書を携えて呪文を使いこなせば、マウス操作では得られないWindowsの本当のパワーを引き出すことができる。Windows10まで完全網羅した本書は、Windows使いのよきパートナーだ。
これはWindowsユーザーが持っておくべき一冊だと
エバンジェリストに学ぶ成長企業のためのワークスタイル変革教本Vol.1 workstyle innovation編 (ワークスタイル変革実践講座(NextPublishing))
内容紹介:
働き方変革が、企業の成長エンジンを変える!
エバンジェリストが語る、これからの働き方。
西脇さんが出ているので購入w
内容紹介:
金融とITを融合した新たな動き「FinTech」は、従来の金融サービスでITを活用するにとどまらず、スタートアップが次々に生まれ、ユーザーにとっての使いやすさを第一とする新たなサービスを生み出し、金融サービスの概念そのものを変えつつある。FinTechが今なぜ話題なのか、それを支える技術と背景から、提供されている金融サービスとそのプレーヤー、ユーザーにとってのメリットまで、日本でFinTechサービスを提供する第一人者がわかりやすく解説。FinTechがもたらす金融の未来も占います。
FinTech はこれから爆発的に浸透すると考えており、徐々に実業にもかかわってきているので基礎的な内容をこの本で学んでいます。
このほかにも多数ありますが、最近購入したのはこれくらいですかね。